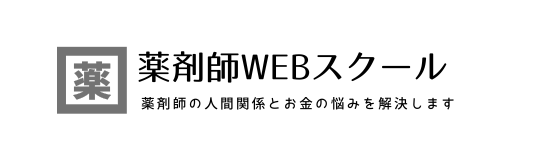新人薬剤師必見!初めての服薬指導のポイント5つ【今日から使える指導例】
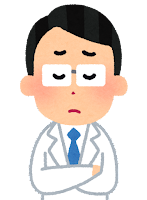
服薬指導をやりはじめたけど患者さんに何を話したらり聴いたりしたらいいか分からないな。
こんな悩みに答えます。
この記事を書いた人 ・調剤薬局で働くこと26年、数々の患者さんの服薬指導にあたってきた薬剤師
服薬指導とは
患者さんに正確に安全にお薬を飲んでもらうための説明
この目的が達成されなければ服薬指導を行ったとは言えません
服薬指導を始めたばかりの薬剤師が押さえておくポイント
5つのポイントに分けて解説していきましょう
服薬指導5つのポイント
- 正確に説明する
- 初回の患者さんにあった説明をする
- 2回目以降の患者さんにあった説明をする
- 患者さんの問題点を知る
- 次回に繋がる服薬指導とは?
正確に説明する

- 薬の名前
- 薬効
- 用法・用量
薬の名前
薬の名前を言いましょう
「この薬はアダラート錠CR20mgと言う名前のお薬です」
患者さんも1回では薬の名前は覚えられないかもしれないけれど、毎回薬の名前を言ってあげることで患者さんも
「私の飲んでいる薬はアダラートか」
と覚えてくれるようになります
★注意ポイント
前回は他の薬局で薬をもらっていた場合、後発品などはメーカーが違う場合もあります
「メーカーが違うので見た目が少し違うかもしれませんが今まで飲んでいたのと同じお薬です」
と補足の説明をしましょう。
「先発→後発」や「後発→先発」も薬の名前が変わってしまうので補足の説明が必要です。
薬効
この薬はなんのために飲むのかを患者さんに分かってもらいます
きちんと目的がわかって飲むのと何の薬か分からないで飲むのではコンプライアンスに雲泥の差が生まれます
「このお薬は血圧を下げるお薬です」
と必ず説明しましょう。
★注意ポイント
薬効が2つ以上ある薬もあります
この時に決め打ちで「〇〇の薬です」と患者さんに説明してしまうと
「そんな症状でかかってないけど?」
となってしまいます。どうすればいいのでしょうか?
「今日は何の症状で病院にかかりました?」
と素直に聞きましょう。患者さんによっては
「何でそんなこと聞くの?」
と問いかけてくる患者さんもいますので、
「この薬は効果が2つあるのでどちらの症状かと思い聞きました」
と説明すればたいていの患者さんは教えtくれます。
用法・用量
1番重要なポイントです
- 薬の名前や効能が分からなくても患者さんが飲んでくれれば薬は効きます
- 1日2回服用するところを1回しか飲まなかったら薬が効かなくなります
- 1日1回服用するところを2回飲んでしまったら副作用が出てしまいます
- 寝る前の睡眠薬を朝飲んでしまったら日中寝てしまうでしょう
用法・用量だけはゆっくりと患者さんがわかるまで何度でも説明しましょう
★注意ポイント
朝食後の薬を飲み忘れてしまった場合はどうしたら良いでしょう
薬によっても違いますが、一般的には朝1回の薬であればお昼又は夜に飲んでも問題ない薬が多くあります
1日3回の場合は2回分を一度に飲まないで飲み忘れてしまった分は飲まなくて問題ないです
初回の患者さんにあった説明をする

その薬を初めて飲むのか、2回目に飲むのか、何度も飲んでいるのかで説明や確認することが変わってきます
初めて飲む患者さんへの説明
薬の名前・薬効・用法です
その他に説明することは副作用です
副作用の説明はどのようにしたらよいのか?
たくさんある副作用で説明した方がよいものはどれ?
頻繁におこる副作用で日常生活に支障を与えそうなものは説明しておきましょう
例えば「眠気」の副作用です
サラリーマンなど日中眠くなると仕事に支障を来しますので眠気が出ることを説明しておくべきです
漸減、漸増の薬の説明
ステロイドの漸減療法で途中までしか薬が出ていない時は飲み終わったら必ず受診するように伝えなければいけません
最悪の場合急に薬を止めることで悪い反応が出てしまうことがあります。
また症状が悪化してしまうこともあります。
アルツハイマーの薬であるアリセプト(ドネペジル)は3mgを14日間ほど飲んだあとに5mgに増量する薬です
これは副作用を抑えるために少量から飲み始めるので、何ヶ月も間が空いてしまうとまた3mgから始めなくてはならず最初の処方が無駄になってしまいます。
14日後必ず受診するように伝えましょう。
他にも初回に注意しなければいけないお薬は沢山あります
2回目以降の患者さんにあった説明をする
2回目以降で考えることは副作用が出ていないかどうかです
「飲んでみて気になることや症状はありませんでしたか?」
初回に副作用の説明をしていたのであれば
「飲んでみて眠気の副作用は出ませんでしたか?」
「その他に気になることなどはありませんでしたか?」
などと聞いてみるとよいでしょう。
ビスホスホネートのように起床時に飲む特殊な飲み方の薬
まずは飲み忘れていないかの確認
飲み忘れたときの対処法の指導
「飲み忘れちゃったから飲んでいないのよ〜」
と言う患者さんは多くいます.
飲み忘れたときの対処法を教えることは最も重要です。
患者さんの問題点を知る
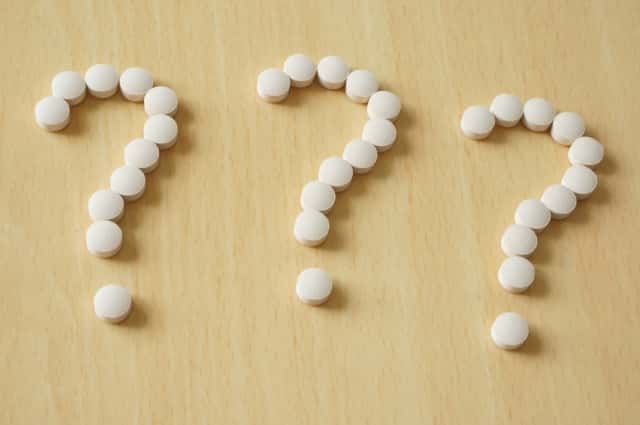
投薬に慣れてきたら患者さんの問題を解決する努力をする
- 患者さんが不安に思っていること
- 患者さんが納得行かないこと
- 患者さんが気になっていること
患者さんが不安に思っていること
患者さんが不安に思うことは
薬を飲んで本当に病気が治るのか?症状がよくなるのか?
と言うこよを患者さんは不安に思います。
この薬を飲むとどうなるのか?
薬理作用や薬物動態を噛み砕いて分かりやすく説明できるようにしておきましょう
★副作用が心配で不安に思っている
この薬を飲んで自分に有害な副作用がおきないか
患者さんは不安に思います。
副作用が出たときの対処方法、また副作用が出たときの予後を分かりやすく説明することで患者さんの副作用に対する不安を和らげることができます。
横紋筋融解症の副作用
スタチン系薬剤が新発売されたあとに横紋筋融解症の副作用がマスコミに取り上げられ不安になる患者さんが激増しました。
「筋肉が溶ける」と報道されて、ただの筋肉痛でも「副作用だが出た!」と薬局や医院に相談しにくる患者さんが殺到したほどです。
横紋筋融解症は血液検査で分かること、すぐに服薬を中止すればよくなることを説明してあげれば患者さんの不安は解消されることがほとんどです。
このような体験をすれば患者さんが不安に思っていることが明確になり、それに対処することもできるようになります
実際に起こったときのために、準備をしておきましょう。
患者さんが納得行かないこと
患者さんが薬を飲んでも症状がよくならない時に、この薬であっているのか?他によく薬があるんじゃないか?
と納得いかないまま薬を飲みつづけている患者さんもいます
何ヶ月があとどうなっているか、1年後、5年後、10年後にどうなっているかを説明すること
そうすれば患者さんが納得して飲んでくれるようになります。
糖尿病の患者さんによくあります
糖尿病は無症状のことが多く、薬を飲んだからといってすぐに何かが変わるわけではありません。
喉の渇きが酷かった患者さんは喉の渇きがなくなるので薬が効いていると感じることができます。
また失明・透析・壊疽は自分には関係ないと思っている患者さんがほとんどです。
これらの合併症の初期症状も合わせて説明しておくとよいでしょう
高血圧の患者さんによくあります
「2日位薬飲んでないけど血圧大丈夫なんだよね」
定常状態にあった薬は少しずつ体内からなくなりますからね。
さて、あなたは患者さんにどう説明しますか?
考えてみましょう!
患者さんが気になっていること
- この薬を飲んでいる時にOTCの風邪薬を飲んでも大丈夫かな?
- 食べちゃいけないものとかあるのかな?
「納豆食べていいの?」
DOACが発売されたあとに頻繁に患者さんから聞かれました。
血液サラサラの薬は納豆を食べちゃいけないと思っている患者さんが昔は沢山いました。
「グレープフルーツジュース飲みたいから血圧の薬かえてもらった」
という患者さんも何人かいました。
食事やOTCに関心がない患者さんのほうがむしろ多いので
「納豆食べてないですか?」
「グレープフルーツジュースは飲みますか?」
など質問することで患者さんに知らせることができます。
次回に繋がる服薬指導とは?

次回に確認できることを説明しよう!
- 患者さんの問題点を聞き出す
- 問題を解決する
- 次の投薬で問題が解決できたか確認する
この3つをセットで考えましょう。
問題点を解決しない服薬指導は1回限りで終わりです。
最初はそんな服薬指導ばかりかもしれません。
薬の説明で精一杯で他のことを考えるのは難しいでしょう。
最初は「今日は暑いですね~」でいいんです。
声をかけ続けることで患者さんから何か質問があるかもしれません。その質問に全力で答えることで少しずつレベルアップしていくのですから。
服薬指導のポイントまとめ

服薬指導5つのポイント
- 正確に説明する
薬の名前・薬効・用法用量
- 初回の患者さんにあった説明をする
必要な副作用の説明をする
- 2回目以降の患者さんにあった説明をする
飲んで気になることはなかったか?
- 患者さんの問題点を知る
患者からのインタビューで問題点を明確にする
- 次回に繋がる服薬指導とは?
1、患者さんの問題点を聞き出す
2、問題を解決する
3、次の投薬で問題が解決できたか確認する
・服薬指導はある日突然うまくなるものではありません。
・毎日コツコツと積み重ねることでうまくなっていきます。
・ただし考えることなく回数を重ねてもうまくなりません。
・どうやったら患者さんの問題点を聞き出して、その問題を解決できるのか。
・これを考えながら服薬指導をすることが上達の近道です。